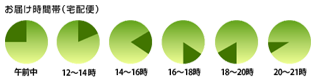店長紹介
ナツメとナツメヤシ
桜前線も北上し、東京近郊のソメイヨシノも見ごろを迎え、春爛漫の様子となっています。
ソメイヨシノはタネを巻いて増やすというより、接ぎ木で増やしていくため、遺伝子がほぼ同じなので、時を同じくして一斉に開花すると言われています。
一気に咲いて、すぐに散ってしまう様には潔さを見出すこともできることから、日本人が好む花とも言われていますね。
さて、そんな桜日和に何をしていたかというと、棗(ナツメ)と棗椰子(ナツメヤシ)のドライフルーツを食べておりました。
名前は似ていても、全く違う木の実です。
棗(ナツメ)は、南ヨーロッパ原産とも中国原産とも言われているクロウメモドキ科の樹木です。
ナツメは古くから食べられている果物で、日本には生薬として伝わったと言われています。
薬だったと考えると、そうとう身体にはいいものなのだな、と想像がつきます。
現在でも乾燥させた棗は、大棗(たいそう)という漢方薬として処方されるほどの薬理作用があるようです。
滋養強壮や精神の安定に効果があり,あの有名な葛根湯にも多く配合されているようです。
そんな棗(なつめ)ですが、香りは甘酸っぱく、実際に食べてみてもほんのり甘く、ほんのりと酸味がある、という感じでしょうか。
見た目と違って、意外と食べやすいお味です。
ただ、昔から「1日に3つナツメを食べると老いることがない」と言われているように、3〜5個くらい食べるのが良いようようです。
私も多くても1日5つまでにしています。やはり漢方薬としても使われるくらいのものなので、食べ過ぎは良くないかな、と思っています。
ドライフルーツだと保存もきくので、本当に重宝をしております。
身体的に元気のない時でも、棗を食べておくととりあえず安心、と思えるようなパワーを感じます。
対して、棗椰子(ナツメヤシ)
こちらは、棗とは全く違う植物で、ヤシ科の木となります。
椰子とついていることから、やはりヤシの実の仲間ですね〜。
こちらは「デーツ」とも呼ばれています。
北アフリカや西アジア(中東)で古くから栽培されていて、その歴史は紀元前数千年にもさかのぼるとか。
なんと、あの聖書に出てくるアダムとイブで有名なエデンの園の中央に植えられた「生命の木」のモデルとも言われている、とても聖なる木なのです。
そんな棗椰子(なつめやし/デーツ)ですが、こちらも生で食べることは少なく、ドライフルーツにしたり、実を煮詰めてシロップにしたデーツシロップにして食用にすることが多いです。
私はドライフルーツもデーツシロップも食べたことがありますが、葛餅などの和菓子についてくる黒蜜みたいな味です。
甘さも砂糖と引けを取らないくらい甘い。
実際にドライフルーツはフルーツというよりも黒砂糖のかたまりを食べているような感じです。
黒砂糖よりも、ちょっとエスニックな風味がありますが、こちらもお菓子を食べているようで、意外と食べやすいです。

左が棗椰子(ナツメヤシ)で右が棗(ナツメ)
棗椰子も食物繊維が豊富でカリウムやマグネシウムなどのミネラル豊富、ブドウ糖や果糖など即効性のあるエネルギー源がメインなので、運動やお仕事などのパワーチャージに効きそうです。
ちなみに、煮物やお菓子作りのお料理などには、棗椰子から採取したデーツシロップが使いやすいと思います。
私は梅酒作りで氷砂糖の代わりにデーツシロップで梅を漬けました。
と、そんな感じで春の日和を過ごしているのですが、花より団子、というか、「花より棗&棗椰子」ということで、この春を楽しみたいと思います。